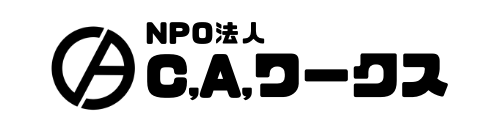役に立たない人間になりたい(自分のこと④)
高校生の頃からずっと思ってきた。役に立たない人間になりたい。政治経済、数学化学。みんなダメ。世の中役に立ちそうだから。役に立たないものほどカッコイイ。ずっとそう思ってきた。そんなおれにヒットしたのは、文学と哲学だった。中学3年のある夜、おれは徹夜して、布団の中で中央公論社版「日本の文学」の太宰治の巻をまるまる1冊読み上げた。すさまじい集中力だ。てきめん目が悪くなって、以来メガネ君になったが、後悔はない。高校生になってからも中央公論社版「日本の文学」を手当たり次第に読んだ。なんせ父親は全集を買い集めるのが道楽だったから、読む本は家にいくらでもあったのだ。おれが心惹かれたのは、坂口安吾や織田作之助などの戦後無頼派や大正時代以降の私小説家の小説だった。ダメな感じ、堕ちてく感じがカッコイイと思った。そこに真実があると感じた。大学もだから、役に立ちそうもない学科を腕によりをかけて選んで受験した。フランス文学科(セリーヌ、カミュが好きだった)、英文科(ヘミングウェイの短編をよく読んでいた)、中国文学科(岩波版『魯迅選集』を高校生の頃読破した)、哲学科美学専攻(ニーチェの中の何冊か、鷲田清一も好きだった)、演劇学科(やったこともなければ、取り立てて好きでもなかったが、父親が演劇鑑賞会をやっていたから、小学校低学年の頃からずっと、月に一本以上のペースで芝居は見続けていた。作るのに手間も時間もかかる。その割には再現もできないし、巻き戻しもできない。おお、役に立たないものの代表だ)、そして日本文学科。7つ大学を受け、結局は日本文学科に進んだ。合格発表が一番遅くて、一番偏差値が高かったという理由でだ。愛知県内の大学は一つも受けなかった。家から出たかった。母親の愛情がものすごくって、このまま家にいたらおれは母親の呪縛から逃れられないと思ったのだ。
教員になって生徒の進路指導をすることが年中行事のようになっている。「ちゃんと将来のことを考えて、しっかり根拠のある決め方しないとダメだぞー」生徒に向かってペラペラしゃべっているが、なんのことはない、自分は「役に立たない人間になりたい」という理由にもならない理由だけで、誰のアドバイスにも耳を貸さずに進路決めちゃったんだから、おまえさ、どの面下げて生徒に偉そうな物言いしてんだよと自分で自分にツッコミを入れたくなる。
それでもおれの「役に立たない人間になりたい」志向は大学選択で気が済んだわけではなく、その後もおれの生き筋の根底になっているようだ。教員という仕事も、演劇も、からだとことばのワークショップも、NPOの設立と運営も、劇場の経営も、これすべて「役に立たないものほどカッコいい」という志向が呼び寄せた選択のように思える。ちゃんと1本、筋を通して生きてる。おれ、結構カッコいいかもしれんな。