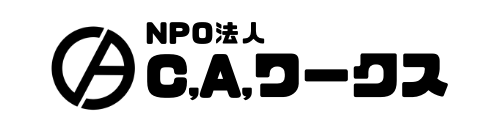「生の言葉」「悪の自覚」
哲学者・鶴見俊種の「教育再定義への試み」を読み返した。最初の章から引用する。
「敗戦直後には、生徒にあやまって、温顔をもって対した教師たちの心むきは、五〇年後には、戦後の経済成長というトンネルをぬけて、遅刻にたいして鉄のムチをふるう別の精神のイガタにうちなおされた。朝、教師は校門に出て、男生徒の頭髪がながくなってないかどうかをしらべ、女生徒のスカートが膝下何センチかのきまりを守っているかどうかをしらべ、その上でしか、門をとおさないとこが、一校ではなくある。芹沢俊介の書くように、学校は戦中から戦後へとファシズムを温存するトンネルの役割を果たした。途中数ヶ月、トンネルがきれて青空のもとに教室がおかれたことはあったが。」・・・A
この本が刊行されたのは一九九九年(平成11)。引用した箇所に先立つ部分には、一九九七年に神戸で起きた、俗に言われる「酒鬼薔薇聖斗事件」に触れて、こんな一節もある。重ねて引用する。
「同時代をゆるがしたこの事件について、私は内部からそれを論じることができない。だが、少年のかよっていた学校長が、学校で全校生徒を集めてこの事件に何もふれないで、生命を大切にするようにという一般論の訓辞をしたということにも、共感できない。おなじ校長が新聞とテレビに対して、事件を重く受け止めているという、大臣や次官や銀行や証券会社の重役とおなじく型どおりの言葉づかいで自分を守っていることにも共感できなかった。教師は、官僚、商社重役と同じ言葉づかいに追いつめられたというのが現在の日本である。親もそうなったらどうなるだろう。そして子どもが親にたいしてそうなったらどうであろう。心のこもらぬきれいな言葉だけが日本全体をおしつつむ。「おとうさんの言われることをぼくは重く受けとめます」と子どもが親に言うとき、ここが、日本の教育に対して逆転機になるのではないか。」・・・B
二〇二六年現在、教員はどんなふうか。二十七年前に鶴見俊介が憂えたような在りようから少しはマシな方向に変わってきたか。
オレは平成元年に愛知県の教員になった。長いこと教育の現場に身を置いてきた。
Aのような指導を、おおっぴらにやってる学校は少なくなったんじゃないか。でもね、自浄作用で少なくなったわけじゃない。いろんな事件があって世間からあれこれ言われたのと、生徒の抱える問題の質が変わってきたせいだと思う。
Bで指摘されているような言葉づかいは一九九九年当時よりも蔓延し、それ以外の言葉を発することのできる教員/発しようという気概のある教員は、見つけ出すのに苦労するのが現状なんじゃないか。オレはね、これ、ものすごくヤバいことなんじゃないかと思ってるんだ。
言葉づかいというのは怖ろしいものでね、そういう言葉づかいをしていると、言葉づかいが内面化されて、思考もその言葉づかいみたいになっちゃうんだ。そうとしか考えられない人間になっちゃうんだよ。
今、教員は、一九九九年に鶴見俊介が上記引用の文章を書いた当時よりも、遥かに怯えているし、臆病になっているし、自分では自覚せぬうちに「型どおりの言葉づかいで自分を守っている」。これが長いこと、現場に身を置いた者の実感だ。
そのわりに心の中では、「自分はイケてる」と思って、生徒よりも自分の方が上だと思っている「オレ様」の教員がムチャクチャ多い。臆病なくせに「オレ様」なんだよ。あのさ、たかが教員採用試験に受かったくらいで、何の「オレ様」やねん?そういう教員見るとね(このごろとみに見る機会が多いんだけど)、反○が出るよ。
「型どおりの言葉づかい」(オレはこれを「社会の言葉」と呼んでいる)ではなく、体裁を取っ払った、実感に基づいた「生(ナマ)の言葉」を必要に応じて発することが出来ること。自分なんて大したことがない、ろくでもない人間だという「悪の自覚」を持つこと。この2点を自分の中に把持し続けないと、生徒に届く言葉なんて発することできねえよ、とオレは思うけどな。少なくとも「リベラルアーツ国語」の授業をやるには、この2点の把持はマストだよ。
年取るとイヤなもんでね、「なんで先生の言葉は生徒に入っていくんですか」なんて、おべんちゃら半分で訊かれることがあるわけよ。訊かれたからって、いい気になって蕩々としゃべったら、「年寄りが偉そうに💢」って感じになっちゃうだろ?だから、ブログに書いたんだけどさ。それでも何だかエラそうで、読み返すとちょっとヤになるな。
でも、「生の言葉」と「悪の自覚」ね。これは本当に大事だとオレは思うよ。