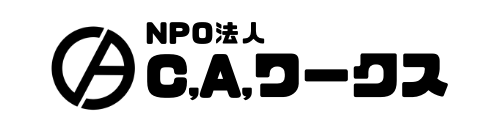自分のこと①
お盆です。死んだ人が帰ってくる期間です。迎え火炊いて、雪洞に灯を入れて・・・。死者が迷子にならぬよう、ちゃんと帰って来れるよう、心を尽くして準備して・・・。おれは一切やらないが、いいなと思う。美しい行事だと思う。
母親が死んで今年は3回忌。坊主に催促されて一応お経をあげてもらうが、単なる付き合いだ。前回のブログにも書いたが、おれのなかに残っている記憶がすべてだとおれは思っている。おれがふとした瞬間に父親を思い出す。それが父への供養だ。「さあ困った」って場面で、母親の姿を心の中に思い描いて「たすけて」と話しかける。それが母がこの世に生を受け、おれとともに生きたことの証だ。
それにしてもこのブログのおかげで、両親や祖母のことを随分思い出させてもらった。ありがたいことだと思う。思いつくままに好き勝手に書かせてもらったが、死人に口なし。父親も母親も祖母も誰も文句を言ってこない。「あんなこと書いて、恥ずかしいったらありゃあしない!」誰か夢に出てきて言ってくれればいいのになあ。
そんなことを考えていたら、そろそろ自分のことも書かないと、という気になった。書かなきゃフェアじゃないって気になった。
しかしながら自分のことを書くのは難しい。自分のことはよくわからない。自惚れもある。自信のなさもある。自分に対してはなかなか客観的になれない。
甘えているようで悪いが、まずは架空のインタビューを受けているという体で書かせてもらう。
<自分を巡る架空インタビュー>
「どんなお子さんでしたか?」
「過保護に育てられた子どもだった。おれ一人っ子なんだよ。ホントは上に兄弟がいたらしい。母親は体育の先生でね、授業でグランドにいたら、サッカーボールが飛んできて、お腹に当たって・・・それで流産したんだって。おれが中学1年の頃、おばあちゃんがこっそり教えてくれた。双子だったらしいよ、おれの上の兄弟は。そんなことがあって、何とかそのショックから立ち直って、それでやっと生まれてきた子どもだからね、おれは。そりゃあ過保護になるわな。両親は共働きで夜にならないと帰って来ない。その代わり、おばあちゃんがベターッとおれに張り付いて、ずっと世話してくれた。やっと生まれてきた大事な子どもを、両親のいない間、見守っているのが自分の役目だっておばあちゃんは思ってたんだろうな。小学校卒業するまで、おれ、一人で外に遊びに行かせてもらえなかったもん」
「え?一回もですか」
「そうだよ。一回も。」
「窮屈だなとか、息苦しいな、とか思いませんでした?」
「全然。でもね、小学校も3年生とか4年生とかになると自転車乗れるようになるから、ちょっと遠くに住んでる友だちのとこ行って遊ぼうよ、とかなるじゃない?おれも何回か遊ぼうって誘われた。誘われるとその時は断れなくて『いいよ』とか嬉しそうに答えちゃうんだ。おばあちゃんが絶対に行かせてくれないってわかってるのにさ。『いいよ、行くよ。何時に行けばいい?』なんてね。答えたあとで、さあ困ったってなってたよ」
「結局、遊びには・・・」
「うん。行かない。翌日になって必死で言い訳するわけ。『行ったけど、場所わかんなかった』とか『急に家の用事で親戚の家に行かなきゃならなくなっちゃって』とか。そんなことが何回も続いて、アイツ約束しても来ないからってなったんだろうな、誰も遊びに誘ってくれなくなった。恥ずかしかったんだよね、学校から帰ったら外に遊びに行かせてもらえないって友だちに知られるのだけは。だから約束しちゃう。で、ウソついちゃう。ほら、おれ、口うまいじゃない?今思うとあの頃鍛えたのかもしれないな、口でうまいこと言ってなんとか窮地を脱する術をさ。でも、もっと自由がほしい、とかたぶん一遍も思ったことないよ。お母さんが夕方にならないと帰って来ないのは淋しかった。でも、それだけ。学校から帰って、家で一人で遊んでいても全然それで満足していたような気がする」
「そうなんですか・・・退屈だなとかも思わなかったんですか」
「全く思わなかったよ。おれ、ずっと一人でおもちゃの人形とかで、お話作って遊んでたんだ。ちゃんとストーリーのある話を一人で頭の中で考えて、両手に人形持って、人形同士を戦わせたり、しゃべらせたりしてね。学校終わって帰ってきて、夕方お母さんが帰ってくるまでの数時間、テレビの置いてあった居間でお話作ってずっと一人遊びしてたよ。台所でおばあちゃんが晩ご飯作っている音、聞きながらね。考えてみれば今もあんまり変わらないな。だって芝居書くのって一人っきりの作業じゃない?いっしょだよ、小学生のおれが居間で人形動かしてお話こさえてたのと。人形が人間の役者になっただけ。やってることは今も昔もいっしょって気がするね」