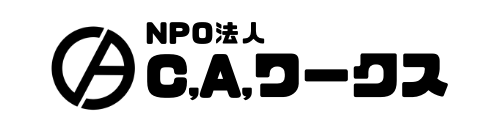手紙(承前4)
父の文箱に入っていた手紙をやっと判読し終えた。鉛筆の字は時が経つと薄くなり、ほとんど読めなくなる。夜なべ仕事に少しずつ解読していった。シンドい作業だった。
その後の父親(手紙の中の「坊ちゃん」)について記しておく。岡崎中学校を卒業して名古屋大学に進んだ。大学では歴史を学んだ。大学卒業後は高校の社会科の教員になった。労働運動に傾倒して、教員の組合の副委員長も務めた。
大きな造り酒屋の次男坊だった父親が、大学卒業後、どうしてあんなに労働運動にのめり込んだのか、ずっと疑問だった。
戦後、民主主義が急速に広がる中で、時流に乗って労働運動にかぶれたのだろうと思ってきた。
しかし今回、「手紙」を読んで、もしかしたら時流に乗っただけではないのかもしれないと、おれは初めて思った。
手紙の末尾に「坊ちゃんには、私は見つけられませんよ」と書いてあった。あのひと言が父親には堪えたのではないか。堪えて、見つけられる人間になりたいと思ったのではないか。だから、労働運動を自分の生きる軸にしようと決意したのではないか。甘ったるい想像かもしれぬが、おれはそう思った。もし、そうなら、単に時流に乗って軍国少年から民主主義者へ転身したというより遥かにかっこいい。筋が通ってる。
父親の日記を昭和20年の8月から12月の分だけ読んでみた。
10月あたりから「帰りに松本」という記述が何度も出てくる。2日に一度くらいの割合か。しかし11月の終わりを境に、「松本」という文字が一切見られなくなる。
戦後、父親は、手紙の「私」を見つけられる人間になれたのだろうか。
膨大な蔵書と、小学校からずっとつけていた日記の束と、そして一通の「手紙」を残し、父は69歳でこの世を去った。