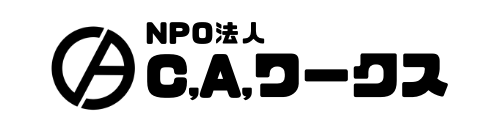家庭教師
中学校1年から3年まで、オレには家庭教師がついていた。母親の教え子のT君が週に二日ほど家にやってきた。T君は大学生だった。
家庭教師といっても、取りとめもないおしゃべりをするだけで、勉強などほとんど教えてもらわなかった。母親は何の目的でT君を雇ったんだろう。
オレはとても背が低かった。背の順で並ぶとクラスで1番前か前から2番目くらいだった。
オレはとてもぼんやりした子供だった。テストというものがなぜあるか、中学生になっても考えたこともなかった。テストが終わると1から5まで成績がつく。学年順位が出る。通知票を先生からもらう。もらっても見もしなかった。まったく興味がなかったのだ。
オレはからだの弱い子供だった。小学校5年生の時、初めて喘息の発作を起こした。以来、長距離走などは怖くて走れなくなった。
オレは楽器が一つもできなかった。小学校5年生の時だ。音楽の授業中にたまたま上手にリコーダーを吹いた。女の先生がクラスのみんなに言った。「兵藤君だってこんなふうに吹けるんだから、みんなもちゃんと練習しなさい」と。「兵藤君だって」と言われた理由はわからない。きっとオレはリコーダーなんかまともに吹ける子供だと思われてなかったんだろう。オレはその言い草にとても傷ついた。以来、楽器を練習することを一切拒否するようになった。
オレは友だちがいなかった。おばあちゃんが外で遊ぶことを許してくれなかったからだ。誘われても、毎回ウソを言って断る。断り続ければ、そのうち誘われなくなる。
オレは本を一冊も読んだことがなかった。父親は大の本好きで家にはいたるところに本があったし、誕生日ごとに一冊ずつ本を買ってくれた。でもオレはその誕生日ブックを一冊も読んだ記憶がない。
こうして書き連ねて見ると、母親がT君を雇いたくなる気持ちもわからないでもない。背が低く、運動もできず、勉強もしようとせず、友だちもおらず、本も読まず、ひたすらぼんやりして日を過ごしている我が子を見て、母親は(或いは父親とも相談したのかもしれないが)見かねて、何とかしたくて、藁にも縋る思いでT君を雇ったのではないか。このままではダメだ。なんとかしないと。でも、どうしていいかわからない。でも、でも、とにかく何か刺激を与えないと。そんな感じでT君は家庭教師としてオレの前に現れたのではなかろうか。
勤めている高校の授業で「アルジャーノンに花束を」という小説を扱った。主人公のチャーリーはIQが68しかなくて、工場仲間にばかにされてオモチャにされているのに、そのことに気が付かない。バカはバカにされていることすらわからないのだ。
中学校2年までのオレも、自分じゃあまともなつもりだったが、まわりから見たら精神薄弱の子に見えたのかもしれない。
中学2年の終り頃、オレは急に目覚めた。意識がはっきりとした。勉強する気になった。運動もする気になった。背もメキメキ伸びた。なんとか県下有数の進学校に滑り込んだ。高校時代にIQを測る機会があった。オレのIQは160だった。
オレが急に目覚めたのはT君のおかげではない。T君はオレに何も与えてくれなかった。しかし、T君を雇うほど、オレのことを身も世もなく心配してくれた人間がこの世にいたこと、なんとも切なく、有難い。子ども時代の甘美な思い出だ。
オレは今、次の芝居のテーマとして、家族のことを考えている。ずっと考えている。そしたらT君のことを思い出した。T君を雇うに至った親の気持ちを想像してみたくなった。それが、こんな文章を書いた理由である。
オレは人恋しいのかもしれない。