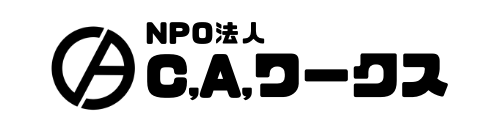卒業
3月1日は卒業式だった。
国語の教員なので、卒業式の答辞や送辞を指導することがある。今年は答辞の指導をした。強烈な体験をしている生徒の場合は書きやすいが、難航する生徒もいる。今年は難航した。
おれ自身、高校の記憶はほとんどない。クラスのメンバーも授業の内容もまるで覚えていない。唯一記憶しているのは、3年間続けた卓球部のことだけだ。練習をさぼって部室でセブンブリッジに興じていた。部室の、汗とカビの混じったような匂いだけは、40年以上経った今でも昨日のことのように思い出せる。
おれの高校3年間の記憶は、おばあちゃんのことで占められている。
おばあちゃんは、おれが中学1年の頃からボケはじめた。高校2年の頃には、外から鍵をかけて、部屋に閉じ込めておかないといけないほど、ボケが進んでいた。それでも徘徊して何度か行方不明になった。
おばあちゃんの部屋からは糞尿の匂いが絶えずしていた。壁にウンチを塗りたくるのだ。仕事から帰ってくると、母はおばあちゃんを罵った。一日働いて疲れて帰ってきて、部屋中がウンチまみれになっていたら腹も立つだろう。それでも母の言葉は苛烈すぎた。聞いている方が辛くなるような言葉だった。おれはおばあちゃん子だったから、母の言葉を聞くのがとてもシンドかった。高校生のおれは、シンドいなあと心底思っていたが、何もしなかった。母を止めることも、おばあちゃんのウンチの世話をすることも何もしなかった。おれは、あの頃のおれを徹頭徹尾恥じている。イヤなら何かしなきゃダメなのだ。傍観者は、ズルい。
おばあちゃんは、おれが大学に受かったのを見届けて死んだ。69歳だった。ボケるには早すぎる年齢だ。葬式を3月に済ませ、東京の大学に進学するために家を出た。以来、実家には住んでいない。
おばあちゃんの葬式が、おれにとっての卒業式だった。おばあちゃんは何があっても味方してくれるし、守ってくれる。子どものころのおれは一点の疑いもなく信じていた。甘やかな子ども時代だった。そのおばあちゃんがいなくなってしまったのだから、それは卒業だ。甘美な子ども時代からの卒業だ。
生徒の私生活を根掘り葉聞き出して把握しようとする教員がいるが、おれは大嫌いだ。人の家の事情や生徒の内面に、土足で踏み込むことは決してしないでおこうと心に誓って教員を続けてきた。
どんな生徒にも、言いたくないことはある。それぞれの事情や思いを抱えながら、生徒は平気な顔を作って学校へ通って、そして卒業してゆくのだ。