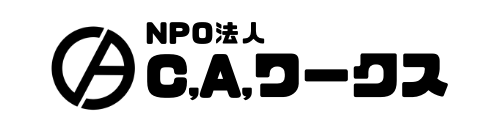アトリエ公演
長いこと芝居を作っていると、手が決まってくる。作品が似たり寄ったりになってくる。
一読して、あ、これは誰それの書いた作品だとわかることはとても大事だ。それを作家性と呼ぶのだろう。そんなことは勿論わかっているのだが、オレは手が決まって、そこから変化できなくなる方が怖い。ほら、年を取ると、からだが固くなるじゃない?それとおんなじでさ、きっと精神も固くなりがちなんだと思うんだよ、年を取るにつれて。前もこのブログに書いたと思うけど、死体は完全に固まってるからね。オレは怖いんだよ。自分の精神が徐々に固まってゆくのが。
明日、アトリエ公演をやる。『膝下のアンブシュア』という作品だ。オレが書いたわけではない。オレは演出をした。決してオレには書けない類いの作品だ。それをなんとか理解し、演出をした。とても難解な、しかし美しい作品だ。実験的な作品でもある。オレはこの作品を、歓びを感じながら演出させてもらった。
加藤周一に「文学とは何か」という1冊があって、オレの高校生の頃からの愛読書だ。加藤周一はいい。文章が乾いていて論旨が明快だ。持って回った言い回しがひとつもない。その本の中で、加藤周一はこんなふうに文学を定義していた。「文学とは、何が真か、何が美か、何が善かを追求する営みである」と。違っているかもしれない。今手元にないから確かめることができないが、違っていたって構わない。オレはそう読んだんだから。
オレの芝居は、真善美の「真」に傾く傾向がある。それはなんとも抗えない、オレの性分だ。その性分が悪いなんて思っちゃいないし、悪いと思ったって今さら変えることもできない。
だが、変えることができないと言って開き直っていたんじゃあ、精神はこのまま硬直してしまう。そして、そのうち、何も創り出せなくなってしまう。それは、オレにとっては精神の死を意味する。そうならないためにも、自分と志向の違う作品に係わることが、今のオレにとってはどうしても必要不可欠な気がしたんだ。
今回アトリエ公演で扱う作品は、明らかに真善美のうち、「美」を追求したものだ。「美」だぞ、「美」。すごくねえか?「便所くん」なんてタイトルを平気でつけるオレが、「美とは何か」を追求した芝居の演出をしたんだから。
しかし、自分のソデを増やすために、精神の硬直に抗うために、儲けなんか度外視して、実験的な作品を作ってアトリエ公演できるってのは、なんと恵まれてることか。自分のスタジオを持ってるからこそできることで、余所で会場借りて芝居を打っている劇団じゃあ、決してできない試みだ。
せっかく苦労してスタジオ維持してるんだ。これからもアトリエ公演、バンバン打とう。
思い出した。つかこうへい劇団の写真集、「前進か死か」ってタイトルだった。外連味のある、良いタイトルだ。