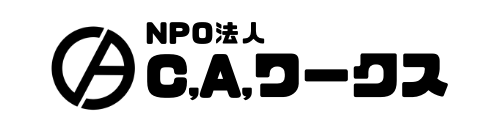場所
私が幼い頃からいっしょに過ごして、ウル家族と思っているところの人間たちー父、母、祖母ーは、みな岡崎の実家で息を引き取った。病院や施設で死を迎えるのが、今では普通のことになっているようだが、それと比べるとウル家族全員が自宅で往生を遂げたというのは、珍しい例なのではないか。私の近しい人の父親は、死期を悟ったとき、自宅に帰りたいと入院先の医師に懇願したそうな。人によっては、自分の生そのものと言っていいほどの愛着を持つ〝我が家〟で終焉を迎えられるというのは、死までも人知の及ぶところと言わんばかりに管理の進んだ現代社会にあっては「僥倖」とも言っていいのかもしれぬと思わないでもない。
祖母は玄関入ってすぐの、ずっと居室に使っていた部屋で死んだ。父は、私が一人で眠れるようになってからずっと〝勉強部屋〟として使っていた、応接間の横にある4畳半ほどの小部屋で、これも私が使って眠っていたベッドの上で死んでいった。母は、1年以上に及ぶ寝たきり生活を経て、レンタルの介護用ベッドが置かれていた応接間で死んでいった。実家で唯一のフローリングの部屋である応接間は、段差もなく、介護にはうってつけの部屋だった。
今は住む人もいなくなってしまった、私が18まで住んでいた実家の3つの部屋には、それぞれその場所で死んでいった3人の死の記憶が、今でも色濃く残っている。
私は本当にウル家族の3人を大事に思っていたし、今でも思っているのだが、3人とも命が尽きるその瞬間には立ち会っていない。それは偶然の不運なのか、それとも命尽きる瞬間を目の当たりにするのが怖ろしくて、その決定的な瞬間から私自身が無意識裡に逃げ出したのか。定かではないが、私は後者であると密かに思っている。そしてそのような自分を唾棄すべき臆病者だと思い続けている。
いずれにせよ、私は3人の死をこの目で確認していない。生きて動いていた人間が、もの言わぬ物体(死体)に変わる、その決定的な、二度とは訪れない瞬間に立ち会っていないのである。私が駆けつけたときには、すでにその決定的な瞬間は終わって、そこにあるのはもの言わぬ物体(死体)だけであった。それが3人続いた。生者から死者へ変わる瞬間をこの目でに届けていない以上、私の中で死を受け入れきれない気持ちが残存するのは当たり前ではないか。18で母が死んだ。35で父が死んだ。57で母が死んだ。母が死んでから4年。無人と成り果てた実家に足を運ぶ度、3人が死んでいった3つの部屋に入る度、私はいまだに3人の気配を感じる。そしてその幾瞬間か後に、まだ3人が生きていていたころの、安心で、この時間が永遠に続くと思い込んでいた18までの実家の様子が私の裡に蘇る。モノを思い切って処分してしまって、今では往事を偲ぶキッカケになるものすらなくなったガランとした器に過ぎなくなってしまった実家が、人の気配があって、台所からは煮炊きする匂いが流れてきて、笑ったり、怒ったり、泣いたりという営みを営々と続けていた頃の実家に変貌するのである。
家には記憶が宿る。記憶を抱いている者が生きている間は、いかにそこに住む人がいなくなっていようとも、記憶を抱いている者にとっては、そこは往事の気配を色濃く孕んだ場所なのだ。
瀬戸内寂聴の「場所」という小説を思い出した。思念が残っている場所を寂聴が再び訪れて、今と往時を心の中で往還するという仕掛けの小説だ。とてもいい小説だ。
それぞれの場所には、誰かの記憶が地層のように折りこめられているのだ。怖ろしくも哀しいことである。