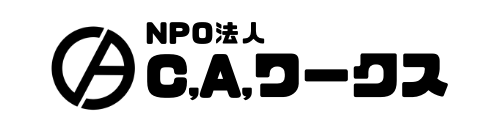(特別編)私はいかにして「リベ国」の授業に至ったか
一、「リベラルアーツ国語」という授業の特徴
「リベラルアーツ国語」の授業を刈谷東高校昼間定時制でやっています。開講から1年が経ちました。刈谷東高校は、不登校を経験した生徒、外国にルーツを持つ生徒、何らかの特性のある生徒、その他いろいろな生徒が通ってきています。多様な生徒たちが、自分に籠もってしまうことなく、違うタイプの生徒とも関係を作れるように、そして、社会に出てなんとか生き延びていけるようにと願って作ったのが、「話すこと、聞くこと」の授業「リベラルアーツ国語」です。
国語という教科には、「読む」「書く」「話す」「聞く」という4つの学習領域があります。「リベラルアーツ国語」は、その中の「話すこと、聞くこと」を学ぶ国語の授業です。私が中心になって授業をやっていますが、私以外の国語科の先生も授業を受け持っています。毎時間、学習指導案という授業プランを私が作り、毎週1時間、授業担当者全員で打ち合わせをする時間をとって授業のねらいや内容を共有してから、授業をやってもらっています。
「リベラルアーツ国語」はとても特徴のある教科です。特徴は5つあります。
1 演劇の基礎レッスンとインプロ(即興)を、授業内容の軸に据えていること。国語の授業ではあるが、座学(座って勉強する授業形態)ではないこと。
2 演劇をまったく知らない教員でも教えることができるよう、内容を精選して編んであること。
3 ひとクラス単位で教えることができること。しかも、人との関わりが苦手な子でも楽しく授業を受けることができるように、授業内容が工夫されていること。
4 新学習指導要領に沿った評価基準が作られていること。
5 生徒同士の話し合いを必ず授業の中に取り入れていること。生徒同士で話しながら、答えのない問いに向かって力を合わせることが、授業を展開する軸になっている こと。
「リベラルアーツ国語」にたどり着くまでには、長い長い年月が必要でした。その間にあった出来事について、私は、自分がやってきたことなので、すべてを昨日のことのようにはっきりと記憶しています。その時々でいろんなひとに助けられてきました。挫けそうになったときには、賞をくれる人が現れたり、本を書きませんか、とお誘いを受けたりしました。単純なもので、賞をもらえば嬉しいし、本を出しませんかと出版社から言われると嬉しいものです。HP担当者と話をしていて、私がこれまで受賞してきた賞が話題に上ったときに、「それ、なんかすごそうだけど、よくわからないから、説明したらどう?」と指摘を受けました。なるほど、と思いました。一度、整理しておくのもいいかと思いました。以下、私が「リベラルアーツ国語」の授業にたどり着くまでの道程で受賞した賞と事業について書きます。
二 演劇そのものを作る活動
演劇そのものを作る活動も、ずっとやってきました。高校演劇部の顧問として、定時制の刈谷東高校演劇部を3度、全国大会に導きました。中部6県約300校の演劇部の中で、全国大会に進めるのはたった1校です。定時制高校の演劇部が全国大会に進んだことは60年ぶりだと、初めて全国大会に出たときに言われました。ましてや3度にわたって全国大会に進んだ定時制高校は、高校演劇の歴史の中で、私が指導した刈谷東高校演劇部ただ一つだけです。これはちょっと自慢していいことかな、と思っています。高校演劇でもたくさんの賞をもらいました。文部科学大臣賞、全国創作脚本賞、愛知県芸術文化選奨奨励賞、愛知県教育文化奨励賞などです。
高校演劇というジャンルだけではなく、普通の演劇(プロの役者、スタッフといっしょに作って、お客さんからお金を頂戴して公演する演劇)も2017年からずっと作ってきました。大阪、金沢、福井・・・。県外公演も多いです。2021年に一宮スタジオをオープンしてからは、3階の〝シアター〟を公演拠点として、毎年新作を公演してきました。謎解きとのコラボ(『月の光』2023年)、一宮の街とのコラボ(『帰郷』2024年)など、他の劇団では見ることのできない前衛的な試みの芝居を作ってきました。
演劇そのものについても書いておきたいことはたくさんあります。しかし、まずは、「演劇表現」という「リベラルアーツ国語」の前身とも言える授業について、そして「演劇表現」に対して与えられた賞などに話題を絞って書き記しておきます。
なお、刈谷東高校演劇部が全国大会に出場した作品は、『奇跡の演劇レッスン』(学芸みらい社、2015年刊行)に載っています。
三 授業「演劇表現」
2004年、刈谷東高校演劇部は高校演劇の中部大会で文部科学大臣賞、全国創作脚本賞を受賞し、初の全国大会出場を決めました。定時制高校が全国大会に出場するのは約60年ぶりという快挙でした。演目は「Making of『赤い日々の記憶』」。私が作・演出を担当しました。当時部員は4名、全員が不登校経験者でした。地区大会、県大会、中部大会と3つの大会を勝ち抜かなければ全国大会には進めません。5月くらいから芝居作りが始まり、中部大会はクリスマスです。そして全国大会は翌年の7月末なのです。まるっと1年以上、その作品を作り続け、上演し続けなければなりません。4人の部員は、もちろん演劇経験などまったくない生徒たちでした。自分のやりたいことはやりたいが、やりたくないことは決してやりたくない。人に対する共感性も乏しく、意欲が持続しない。不登校を経験した生徒に共通してみられる(と、私は思っています)特徴を、見事に4人は備えていました。そんな生徒たちが協力して芝居を作り、飽きずに稽古を続け、人前で臆さず演じきったわけです。どうして彼らはそんなことができるようになったのか?大会を勝ち進みながら、私はその秘密をずっと考え続けていました。
もしかしたら、とあるとき私は思いつきました。あの基礎レッスンが彼らに変化をもたらしたのではないかと。
私は、芝居そのもの稽古よりも、もっともっと基礎的な演劇のレッスンを彼らにやらせていました。一つの芝居の稽古だけでは彼らは飽きてしまうからです。飽きたら部活にも来なくなってしまうからです。
私が彼ら4人にやらせていたのは、だれかとやりとりをする練習でした。言葉でやりとりをすることができるようになるために、その土台として、まずは、よく見、よく聴き、よく感じ、ひとをひとと思えるようになるような練習をずいぶんと長い時間を割いて彼らにやらせていたのでした。演劇は歴史の古い芸術ジャンルです。やりとりすることを成立させるための基礎レッスンが、膨大に蓄積されています。その中から、適宜よさそうなものを探しだし、目の前の部員たちに合うように変形を施し、彼らの食いつきの悪いメニューはさっさと諦めて、飽きっぽい部員たちでも飽きずに取り組めるレッスンだけを残し、そのメニューに更に変化を加え・・・という作業を、部員たちと延々繰り返していたのでした。芝居そのものの稽古より、基礎レッスンに充てる時間の方が長いくらいでした。
そうか、と私は思いました。もしかしたら、と私は思いました。〝不登校に演劇の基礎レッスンは効くかもしれない〟と。
2005年、刈谷東高校は全国大会に出場しました。全国大会は青森県八戸市でした。無事に全国大会が終わって、私は当時の校長に掛け合いました。演劇の学校設定科目を作りたいと。演劇を通して部員は確かに変わった。そのノウハウを今度は、授業として演劇部以外の生徒のために活用したいと。
そうやってできたのが、学校設定科目「演劇表現」でした。2006年4月開講、2年生から4年生の生徒が受講することができる選択科目でした。愛知県公立高校初の、卒業単位として認められる正式な演劇の授業がこうして設立されたのでした。
演劇部の活動を通して、部員が〝変わった〟という実感からスタートした授業ですが、先述したとおり、芝居作りそのものを通して、部員が〝変わった〟とは私は考えていませんでした。部員は演劇に基礎レッスンを通して、やりとりを学んだことで〝変わった〟のだと私は確信していました。だから、「演劇表現」の授業も「演劇」という言葉を冠してはいるものの、演劇そのものを作ることを目的とする授業ではありません。演劇部員が〝変わった〟。そのために力があったと私が考える演劇の基礎レッスンをやる。具体的には、やりとりの成立に向けたレッスンメニューをみんなでやっていきながら、自分について、他者について、共に在るということについて、自分の心やからだに起きたことを素材として、考えてゆくという内容の授業なのです。
いまでも「演劇表現」の授業は続いています。授業の基本的な考え方は変わっていません。次に記すスーパーハイスクール事業によって、授業のメニューがより精選され、客観性を帯びたくらいで、基本的な構造、目的は変わっていません。授業を受けた生徒が、就職や進学の面接試験でやりとりができて(上手く話せて)、合格してくることが続きました。「演劇表現」の授業を受けとくと、面接が上手くなるぞ、という評判が生徒の間に立ちました。今では40人を超える生徒が毎年受講を希望しています。
刈谷東高校演劇部の活動記録、授業「演劇表現」については、『今、ここに、あなたといること』(角川学芸出版、2011年刊行)に詳しい記述があります。
具体的な授業の内容は、『コミュニケーションの準備体操』(岩波書店、2025年刊行)で読むことができます。新聞にも多く取り上げられました。朝日新聞朝刊教育面「子どもたちは今」(8回連続、2013年)、中日新聞朝刊教育面「子どもとともに」(5回連続、2014年)にも「演劇表現」の授業内容が紹介されています。
四、スーパーハイスクール事業
2008年、「演劇表現」の授業は、愛知県教育委員会より「スーパーハイスクール」の研究指定を受けました。3年間で一つのテーマを研究せよ、という指定です。研究テーマは、〝真のコミュニケーション力向上をめざす演劇表現の学習プログラムの開発〟というものでした。今では考えられないような予算も付きました。以降、2010年までの3年間を使って、演劇表現の教科書を作りあげるという研究に取り組みました。
1年目の研究テーマは「調査」。国内で行われている演劇の授業をくまなく見て回りました。どんな特徴があり、何が問題なのか、授業を参観させてもらいながら、まとめていきました。併せて、演劇と名のつくあらゆるジャンルの公演も観に行って、関係者にできるかぎり話を聴きました。新劇から歌舞伎まで。宝塚歌劇団からアングラ演劇まで。どこの学校とも違う、普遍性を持った、プロの演劇関係者ではなく教員が目の前の生徒のために教えることができる演劇の授業。視察を繰り返しながら、私の中に目指すべき授業がはっきりと像を結んでいきました。
2年目のテーマは「検証」でした。週に2~3回の割合で、学校の仕事の終わったあとに、愛知県内のあらゆる地域を回って、一般の方を対象に出前授業を行いました。刈谷東高校の生徒に効くだけでは、普遍性のあるメニューにはなりません。今を生きるすべての人に有益な授業メニューでなければならないと考えたのです。校内向けには「演劇表現通信」なるプリントを毎週作成し、今何をやっているかを報告しながら進めました。
そして3年目が「執筆」です。2年間の研究成果に基づいて、『演劇表現事例集』(非売品)を執筆し、研究をまとめました。この研究を通して、様々な方と知り合いになりました。日本で初めて演劇の授業を始めた、」演出家の竹内敏晴先生と知り合いになれたのは、私の中で大きな、決定的な出来事でした。「わたしはあなたの応援団長になります」竹内先生はおっしゃってくださいました。そうして、その言葉通り、いろんな支援をしてくださいました。今でも迷うことがあると、「演劇表現事例集」を開きます。拙い部分はもちろんあります。ですが、それ以上に、その冊子の中には「初心」のようなものが生々しい言葉で記されているからです。
五、中日教育賞
2015年、私は、第47回中日教育賞を受賞しました。受賞理由は「演劇的手法によるコミュニケーション教育」です。
中日教育賞とは、「中日新聞社が中部地方9県(愛知、岐阜、三重、静岡、長野、滋賀、福井、石川、富山)の教育の第一線にあって、すぐれた業績をあげている教育者、教育団体を表彰するために、1969年(昭和44年)に制定された顕彰制度である」(ウィキペディア参照)
表彰式は10月30日に中日パレスで行われました。私は、受賞者を代表してスピーチをしました。その中で「賞は今後の活動につながるパスポートだ」と話しました。
私が受賞してから今日まで、愛知県公立高校の教諭は誰も受賞していません。
教育に関する賞は、日本では数が多くありません。その中でも長い歴史を持つこの賞を、私が個人として受賞できたことは、素直に嬉しかった。この賞を受賞したことで、他県からの出前授業の依頼が増えました。
六、愛知県教員表彰
2016年に愛知県教育委員会により、私は優秀教員に選ばれました(愛知県教員表彰)。表彰に係わる実践内容として、資料にはこう記されています。「演劇的手法を用いたコミュニケーション力向上の教育プログラムを開発・実践し、成果をあげた。文部科学省の「児童生徒のコミュニケーション能力の育成に資する芸術表現体験」事業の講師に委嘱されるなど、校内だけではなく全国各地で出前授業を行い、普及活動にも努め、高い評価を得ている」