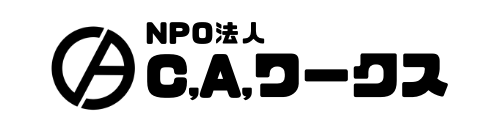知己を見つける
大学2年の秋から冬にかけて、ぼくは井之頭公園裏のアパートに閉じこもって暮らした。所属していたサークルから足を洗って、友人とも連絡を絶って。大学も一日も通わなくなった。
愛知県の岡崎市から上京して、大学に入った。1学年1万人も学生がいるマンモス大学だった。18歳のぼくは、東京に行って愕然とした。自分がいかに田舎者で、遊びの一つも知らないことに気づいたからだ。ぼくは狂ったように遊ぶことを自分に課した。以来2年少しの間、今が朝か夜かわからないような、今日自分がどこで眠るか予測できないような、乱れきった生活を続けた。
いくら若くても、そんな生活は長くは続かない。突然、ネジが切れたようにすべてが嫌になった。ある日の真夜中、ぼくはバイクに乗って、それまで住んでいた都内から逃げ出した。どこへ行こうというあてなど全くなかった。ただただ逃げ出したかった。あの喧騒から逃げ出したかった。周りにいい顔をして、チヤホヤしたりされたりする生活から、一刻も早く逃げ出したかった。精神が悲鳴を上げたのだ。
夜が白み始めた頃、ぼくは、吉祥寺駅の南口の丸井の前でバイクから降りた。ガス欠になったからだ。今とちがって、24時間開いているガソリンスタンドなどあの頃はなかった。そのまま駅前で不動産屋を探して、その日のうちにアパートを決めた。
閉じこもって暮らしながら、ぼくは本ばかり読んでいた。吉祥寺にはいい古本屋が何軒かあった。吉行淳之介の『私の文学放浪』も、井之頭公園裏のアパートで読んだ一冊だ。
人生が仕立て下ろしの背広のように、しっかりと身に合う人間にとっては、文学は必要ではないし、必要でないことは、むしろ自慢してよいことだ。(吉行淳之介「文学を志す」より)
吉行淳之介は孤独を描いた作家だ。井之頭公園裏に引きこもっていた20歳のぼくは、彼の描く孤独に感応し、そして救われた。知己を見つけた気がしたのだ。