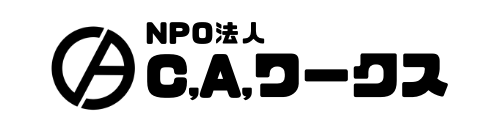『帰郷』バックストーリー⑤
転落2
以来幾星霜を過ごしたか、今日と明日の区別がつかないような旅暮らしを続けるうちに時次郎のからだはブクブクと太り、かつて商店街の希望の星と目された頃の面影はどこに求めようもなくなった。5年経つ頃には、役も与えられず、裏方仕事専門となり果てた。音響補助、照明の手伝い、それもうまくこなせないとわかると、時次郎は切符もぎりと会場整理専門のスタッフになった。肥え太った時次郎の額には、真冬でも少し動くと大粒の汗が光り、息が上がった。床に滴り落ちる汗を見て、お客は気味悪がった。切符もぎりでも会場整理でも、時次郎は本当は要らないスタッフだと思われていたのだ。
それでも時次郎は劇団から離れようとしなかった。妻も子も仕事もすべて投げ出して、この道に入ったのだという自負、自責の念だけは、肥え太った体の中で、埋火のように消えることはなかった。今更ね、時次郎は大広間の雑魚寝の布団の中で時折つぶやいた。今更どの面下げて戻れるってんだ。
こうして時次郎は15年もの間、旅回りの劇団にしがみつくようにして生きた。
帰りなん、いざ
ある日、団長に突然呼ばれた。「時さん、おまえさん、いくつになる?」団長は話を切り出した。
「50になります」時次郎は答えた。
「そう。わたしゃ、もう60よ。このごろじゃあ旅打ちがすっかり堪えるようなっちまった」
団長は電子タバコをジャージのポケットから取り出して、せわしなく吸い始めた。
「アイコスですか」時次郎は何げなく尋ねた。
「うん、ニコチンが少ないんだってさ、これ」
二人は、鳥取駅前の健康ランドのソファに向かい合っていた。深夜2時の健康ランドのロビーは、老人二人以外、誰もいなかった。
「時さんは、何吸ってるの?」団長が訊いた。
「わかばです。安いですから」
「そう・・・。安いのはいいよね」
再び、深夜の健康ランドのロビーは静寂に包まれた。団長は一本吸い終わると、すぐに新しいカートリッジを装着した。
「これ、2本まで続けて吸えるんだ。世の中どんどん便利になるな」
「おれも替えようかな、アイコスに」時次郎は愛想よく話を合わせて言った。
「娘がね。東京にいるんだ」団長は言った。「そろそろ落ち着いてもいいころじゃないってこの頃しきりに言うんだよ」
「・・・」
「でね、時さん」団長は意を決したように言った。「わたしね、この旅公演が終わったら、東京の娘んとこで、世話になろうかって思ってるんだ。会社もさ、本社で仕事、用意してくれるっていうし」
「・・・そうなんですか」時次郎は他に言う言葉が見つからなかった。
「ついては、時さん」団長は話をつづけた。「おまえさんも、そろそろ一宮に戻っちゃあどうかな。言いにくいんだけどさ、次の団長がね、おまえさんはもう要らないって言うんだよ。いや、もちろん、わたしゃ、反対したよ。何言ってんだい、時さんは15年もこの一座を支えてきたんだ、いわば一座の大黒柱だよ。柱はね、そりゃあ普段はだあれも意識しやしないさ、でもね、柱があるから家は建っていられるんじゃないか、いざというとき支えになるのは、何があっても、いつ何時でも、必ずそこにいて、どっしり構えてくれている、そういう大黒柱のような存在なんじゃないのか、おまえさんみたく、ちょっと若くて勢いのあるだけのお兄さんにはわからないかもしれないけど、時さんはね、おまえさんがまだ女の子の手も握ったことのないようなガキの時分からずっと、この一座を支えてきた大黒柱なんだからねってさあ」
アイコスをしきりに吹かしながら、団長は一気にまくし立てた。
いつものくせだ、時次郎は思った。団長はウソを言う時、息も継がずにまくしたてるようにしゃべり続けるクセがある。団長、そんなウソ、言わなくったっていいよ。
「そうですか」時次郎は努めて冷静に言った。「おれなんかのために、そこまで仰ってくれるなんて。時次郎、身に余る光栄です。・・・よござんす。いつかこういう日が来るとは思っていました。お世話になった団長が身を引くと仰ってるんだ。拾ってくれた恩人が身を引くと言ってるんだ。なんでおれだけが、未練がましく劇団にしがみついていられるもんですか。団長、逆にこっちからお願いします。団長と一緒に、この劇団からお暇させてください」時次郎は頭を下げた。
「すまねえ、時さん、ホントに済まねえ」団長は時次郎の手を取り、封筒を握らせた。
「なんですか、これ」
封筒には、ボールペンで〝餞別〟と表書きがしてあった。
「わたしの気持ちだよ。黙って受け取ってくれねえか」
時次郎は封筒を握りしめたまま、また深々と頭を下げた。ボタボタと涙が落ちた。
〝餞別〟のふた文字が、涙でみるみる滲んでいった。
翌朝を待って、時次郎は荷造りをした。15年もいたというのに、ボストンバック一つで十分すべてが収まってしまった。劇団に係わるものはすべて処分した。ただ一つ、それでも捨てられぬものがあった。緑のタイツである。初めて、そしてただ1回、ピーターパンを演じた時に身につけたタイツである。「これだけは捨てられねえ」時次郎は、ズボンの下に緑のタイツを履き込んだ。
団長は今朝は朝から留守だった。東京本社に呼ばれて、朝早く新幹線に乗ったらしいと、今では時次郎の上司になっている20も年下の製作スタッフが教えてくれた
時次郎は誰にもさよならは言わなかった。もとより気にかけて見送りに来てくれる劇団員も一人もいなかった。一人鳥取駅のホームに立ち、姫路行きの「スーパーはくと」を待った。
時次郎の頭の中には、目指す場所は一つしかなかった。あの街、15年前に何もかも打っちゃって、後ろ足で砂をかけるようにして見捨てた街。あの街を一目見て・・・そして。
時次郎はポケットからしわくちゃになった「わかば」を取り出し、100円ライターで火をつけた。吐き出した煙が、山陰の秋空に消えていった。