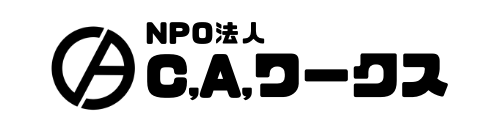『帰郷』バックストーリー③
出奔
平成20年(2008年)35歳。時次郎は突然出奔した。店も家族も商工会の仕事もすべてほっぽり出して、誰にも何にも告げずに一宮の街から姿を消したのである。
16歳高校1年生になる娘、35歳の妻、68歳の老母は途方に暮れた。元々喫茶「まちぶせ」の収入は微々たるものであった。妻は市役所勤め、母はミシンの内職、娘は学校に内緒で飲食店でアルバイトをして、生活費と借金の返済のやりくりをした。
平成21年(2009年)、店の前で転んだのがきっかけで、母親が歩けなくなった。寝たきりになった。洋品店の店先に立つことはおろか、もうミシンも踏めなくなった。時次郎の夢の城はこの時点で、完全にシャッターを下ろすことになった。妻は市役所勤めをしながら、母の介護をした。「まちぶせ」のあった場所に介護ベッドを置いた。
寝たきりの状態が一年半続き、翌平成22年(2010年)冬、肺炎を起こして、母はあっけなく亡くなった。喪主として母の葬儀を取り仕切り、母の死亡保険が入って、そのお金で自社ビルの借金の返済が完了すると、それまで気丈にふるまって一人で何役もこなしていた妻は呆けたようになってしまった。夫婦の部屋に籠って、幾日も出て来なくなった。市役所は心神耗弱を理由に休職扱いにしてもらった。娘は学校に通いながら、家事をして、母を気遣い続けた。
卒業式の日
平成23年(2011年)、娘は高校を卒業した。名古屋市内のデパートに就職が決まっていた。卒業式の朝、シャッターの閉まった自社ビルの前で母と娘は記念写真を撮った。式には母親が来てくれた。黒のフォーマルスーツを着こなした母はまだ38歳で、他所のお母さんと比べても十分に若く、きれいだった。その日、母は久しぶりに笑顔を見せてくれた。この春からはちゃんと働いて、お母さんにラクさせてあげるんだ。娘はそう決意しながら卒業式に臨んだ。その夜は、母親と外食をした。名古屋のちょっといいレストランで二人でお祝いをした。「もう、これで大丈夫よね」母親はごはんをたべながら突然言った。「うん」何の気なしに娘は答えた。
その日の夜中、寝付けずにトイレに起きた娘は、鴨居にぶら下がる母を見つけた。ごはんを食べていた時に母が言った言葉がよみがえった。娘は、母を鴨居から下した。母のからだはまだ温かかった。すぐに救急車を呼んだ。命はとりとめたが、目を覚ました時、母の瞳から正気の光は失われていた。
ホームにて
娘は手荷物だけを持ち、母の手を引いて一宮をあとにした。
こんなに変わってしまうんだ。あっけなく変わってしまうんだ。街も人も変わってしまうんだ。なら、もうなんにも信じられない。信じちゃいけないんだ。一宮駅のホームで母と二人で電車を待ちながら娘は思った。そしてこうも思った。私はあんたを許さないよ。お母さんと、おばあちゃん、そして私を放り出して、突然いなくなったあんたを、私は死んでも許さないよ。
卒業式の朝、母と二人で撮った写真は、母の箪笥の中に置いてきた。もし、と娘は一宮の街をぼんやり眺めながら考えた。もし、あんたがいつかあの家に戻ってきたら、あの写真を見るといい。お母さんも私も精いっぱい笑っている、あの写真を見るがいい。そうして二人の後ろの、もう久しく開けることもなくなったシャッターを見るがいい。あんたにわかるか?お母さんと私の笑顔の下の気持ちがあんたにわかるか?・・・わかってたまるか。あんたを私は許さない。絶対に許さないからね。
手をじっと見ると、母を鴨居から下した時の感触が蘇った。急に不安になって、横に立つ母の手をぎゅっと握った。
商店街の理事長に、娘から手紙が届いたのは、それから1年後のことであった。ビルは商店街に寄付します。好きに使ってください。手紙にはそう書いてあった。消印は東京都三鷹市とあった。手紙の文字はひどく震えていた。娘は病んでいるのかもしれないと商店街の理事長は思った。奥さんはどうなったのだろう。退院した時に一度だけお見舞いに行ったが、もう以前のあの人ではなかったが。しかし、理事長はそれ以上の詮索はしないことにした。この商店街で、商売を続けながら生き延びてゆくことは並大抵のことではない。他人に構っている余裕などありはしない。時次郎のビルは、名義を時次郎から、商店街組合代表の理事長に書き換えられた。娘さんと奥さんは東京で暮らしていると、理事長は商店街のみんなには説明した。
娘と妻が、その後どんな人生を歩んだかは誰も知らない。