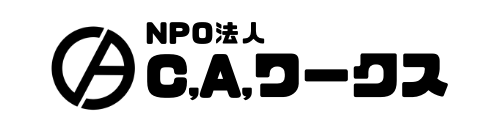家だけが残った。
おれが実家に戻ったのは、母親が家の前の坂で転んで、歩けなくなったという電話を受けた日からだ。
おれは自分のことだけにずっとかまけていた。学校の仕事が忙しいだの、演劇で全国大会に行くだの、演劇ワークショップで全国各地に呼ばれるだのと、言い訳は山ほどあった。でも、そんなのは所詮言い訳だ。おれは、自己中の、こころの狭い人間だった。なぜもっと早く母親のこと、良くしてやらなかったのだろう。おれは気づいていた。母親がよちよち歩きしかできなくなっていることを。たまに会うといつも足をさすっていたことを。靴を脱ぐのを嫌がって、家の中でもずっと履きっぱなしだったことを。おれは気づいていたのだ。それでもおれは目を背け、世話することから逃げていた。
おばあちゃんが死んで、お父さんが死んで、母親はあの広い家に一人で住んでいた。たった一人の子ども(おれのことだ)も寄り付かなくて、徐々に徐々に衰えていく足を抱えながら。どんな気分だったろう。どれほど心細かっただろう。
母親が死んで2年経つ。こんな文章を書いているわりには、おれはもう、母親の月命日も忘れがちになっている。心底薄情な人間だと思う。でも、そんなおれでも、こないだ学校から帰って、真っ暗な実家の前に立って、真っ暗な家を見上げていたら、たまらない気持ちになった。みんな死んじゃったのに、家だけがなんで残ってるんだろう。古くはなっているが、家はそのまま、ちゃんと、あるのだ。おばあちゃんがいて、お父さんがいて、お母さんがいて、子供の頃のおれがいた家だった。夕方学校から戻ると、道に面した台所だけはいつも明るかった。換気扇がくるくると回って、その日の晩ご飯の匂いがした。2階の広い物干しには、洗濯物がはためいていた。天気の良い日は布団を物干しいっぱいに広げて干した。干しながら布団の上でごろごろするのが大好きだった。陽ざしをたっぷりと浴びた布団から、日光の、いい匂いした。
でも、もうだれもいない。仕事から帰っても、台所に明かりは灯ってはいない。物干しに洗濯物がはためいていることもない。
なんで誰もいなくなっちゃったんだろう。なのになぜ、家だけはピンシャンして残っているんだろう。家は、人が住んでいて、初めて家と呼べるんじゃないのか。なら、今、おれが見上げているこの建物は家と呼べる代物なのか。記憶だけをたぷたぷと孕んで、夜の闇の中、佇んでいるこの代物は、一体何なのだろう。おれは真っ暗な家の前にじっと佇みながら空想に耽る。ピンポーンとおれがチャイムを鳴らす。それを合図に台所の電気が点いて、換気扇が回りはじめる。はーいという声がする。鍵を開ける音。がらがらっと玄関の引き戸が開く。「おかえり。寒かっただらあ」お母さんが笑って出迎えてくれる。応接間から煙草の匂いがする。「お帰り」。お父さん、今日は早かったんだな。・・・そんなことをぼんやりと空想すると、胸の奥がじんわりと暖かくなる。そうしてすぐにうんと寂しい気分になる。亡霊でも、幽霊でも、なんでもいいや。もう一遍、おばあちゃんのごはんが食べたい。お父さんとしゃべりたい。元気なころのお母さんに会いたい。
叶わぬ夢だ。みんな、時の滝つぼの中に消えてしまった。でも、もし万が一、奇跡が起きたら・・・。