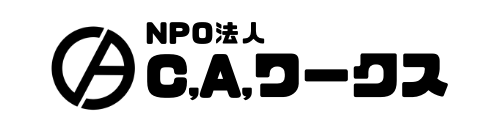別荘を売った
母の別荘を売った。二束三文だった。手続きもあっけないほど簡単だった。
呪わしい別荘だった。別荘の、らせん状になった階段から、母は転げ落ちた。以来、母の足は急速に萎えていった。
足腰が丈夫なら、もっと長生きしただろうに。歩けなくなった自分を嘆きながら晩年の日々を過ごさずに済んだろうに。オレにとっては親の敵のような別荘だ。
母にまつわるものが、また一つ手元からなくなった。自分で決めて売っぱらったくせに、何だかさみしくてしかたない。
父は脳梗塞をやって右半身が麻痺していた。動けない父を、母は自分一人で介護した。息子のオレにすら手を出させなかった。父親の兄弟たちが会いたがっても、全部断った。父は69で死んだ。
父が死んですぐ、母はオレに言った。
「もう、なにしていいか、わからん」
言い方も、声の調子も、ずっと耳にこびりついて離れない。父の介護が母のすべてだった。生きる張りだったのだ。
父が亡くなった時、オレは35歳だった。生の盛りのオレは、母の前に黒々と口を開けていた「無聊」という名の怪物の恐ろしさに、想像が及ばなかった。「好きなことやればいいよ」そんなふうにオレは答えたように思う。なんておざなりな、なんて冷たい言葉だろう!好きなことがわからないと訴えている人間に対して言う言葉ではない。母が絞り出すようにして、心の内を言葉にしてオレに救けを求めたというのに。
父が死んでから、母が死ぬまでに22年間という年月があった。母は22年間、一人っきりで暮らした。家族4人の団らんが確かにあった岡崎市井田町の家で、一人っきりで22年間を過ごした。オレは、心のどっかで気にかけながらも、決して母の許に寄りつこうとしなかった。
このトシになって、オレはようやく思うようになった。もうすべてが遅いけど、このトシになって、やっと思いが及ぶようになった。
22年間、母はどんなふうにして、ひとりぼっちで日を過ごしていたんだろう。
やることもなく、生きる張りもなく、誰も訪れることもない、いつ終わるかわからない時間に、母はどうやって耐えていたのだろう。
オレは報いを受けるだろう。母の無聊を想像できなかった報いを、母の孤独を見捨てた報いを、受けるだろう。
でなきゃ、母に済まないじゃないか。