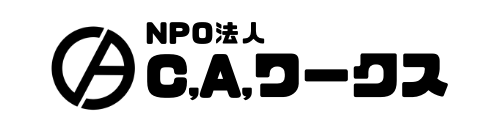ギアチェンジ
愛知県立大学で講演をした。タイトルは「若者はなぜ話しかけるのをためらうのか」。講演と言っても大半の時間をレッスンに費やした。
やったレッスンは、並び替え→箸を挟んで立つ→マイムしりとり→組織論→マイムしりとり
レッスンを始める前に「あなたは、人に話しかけるのをためらいますか?それはなぜですか?」を書いてもらった。
後で集約してみると、参加者の54%は「常にためらう」と答えていた。「親しい人にはためらわないが、親しくない人にはためらう」が41.2%、「ためらわない」が4.8%だった。実に参加者の95.2%は、「ためらう」と答えたことになる。この数字だけ見ると、今回立てた問いは、あながち的外れなものではないだろう。
しかし、もう少し問いの有効性を鍛えないと解に向かって進めない。
たとえば・・・昔の若者はためらったか。今回と同じような数字が出れば、若者というものは話しかけるのをためらうものだ、というテーゼができて、この問いの有効性は消える。しかし、昔の若者に直接アクセスする方法はない。同種のアンケートを昔(これも問題だ。昔っていつだ?それも規定しないと議論が始まらない)、誰かが取っていればいいのだが。
たとえば・・・今の若者以外はためらうのか。今回と同じような数字が出れば、現代を生きる人間は、総じて他者に対して話しかけるのをためらうものだ、というテーゼができる。この場合も、今回立てた問いの有効性は消える。
てな感じで、ちゃんとやるなら、厳密にやっていかなきゃならない。すると結果、長大な論文を書くことになり、今年度いっぱいの委嘱でケリがつくような代物ではなくなる。
不思議なもので、オレの中にこの問題を続けて考えたいなという欲が湧いてきた。
だって、面白そうだもん。問いの正しさを立証して、それへの対策として「リベ国」の授業を分析して、この授業にしかない要素を抽出して、それが参加者にどうヒットして、「はなしかけることのためらい」がどのように、どれくらい低減したかを数値化して、「リベ国」の有効性を立証するというプロセス踏むのは。
あるいは、当事者研究の形を取った方が現実的かもしれない。こっちも面白そうだし、手に余る感じはない。
「やりたいことはやらないと後悔する。人目なんて、人の評価なんて気にしてる場合か」石原慎太郎がYouTubeの番組でこんなことを言っていた。
仰有るとおり。
このブログを読んでくれてるみなさんは、やりたいことをやると心に決めて、自分の生活を制御して生きていますか?それともピンボールの球みたいに、偶然起きる日々の出来事に小突かれ回されながら、その時その時で与えられた役割を右往左往しながらなんとかこなすようにして日を過ごしていますか?
きっと若い頃は後者みたいな感じでも十分生きてるって実感が持てるのしょう。でも、トシをとるとどうなんでしょうか。残り時間も少なくなる。体力もなくなる。第一、小突き回してもらえるほど、周囲から期待もされなくなり、相手にもされなくなる。だから・・・どっかで後者から前者にギアチェンジしないといけないんでしょうね、きっと。でも、それが難しい。ギアチェンジが難しい。その難しさを石原慎太郎のYouTubeは言っているんだろうと思います。