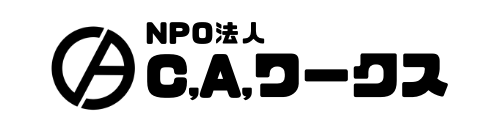〝年寄り〟のロールモデルの創出
先週の土日で「小さな劇場からの脱出」というイベントがあって、オレは演出家の役で計12ステージ、舞台に立った。年を取ると、疲れが後から出る。今週の前半は使い物にならなかった。ようやく足のだるさや、からだの重ったるい感じが今週の金曜日くらい。なんのことはない、ほぼ一週間、ずっと疲れが尾を引いていたってことか。
今日は土曜日で、午前中EQスクールやりに行って、午後直帰していまこれを書いている。これを書き終わったら新しく出そうとしている本の原稿を書いて、明日はまた芝居の稽古で一日大阪だ。で、月曜からは学校に行って・・・。休む間がない。
こないだ敬老の日だっただろ?たまたまスーパー行ったんだよ。ちょうど昼前くらいだったかな。そしたら、いたんだ。年寄りがいっぱい。ウジャウジャいた。なんなんだ、この年寄りたちは!って思ったよ(その日はポイント2倍デーだったんだって。後で知った。なんだよ、年寄り、情報に敏いじゃねえか。ところでポイント2倍デー、ってなんだ?)。
いろんな年寄りがいた。大声でしゃべりまくっている友だち同士の年寄りがいた。ぽつんとひとりベンチに座って、微動だにしない鉱物みたいな年寄りもいた。車出そうとして、交通整理のひと(これも年寄りのバイトだ)がヘタクソだと言って、馬鹿でかい声でクレームをつけている年寄りもいた。その他にもいろいろいろいろ。オレが男だからか、こいつなんなんだって目に付いたのは、みんな男の年寄りだった。
年寄りが目に付いたって書いたけど、落ち着いて考えてみりゃあ、総人口の5人に1人が65歳以上なんだから、目に付くのは当たり前っていえば当たり前なんだけどね。
かくいうオレも年寄りだ。だが、上手く言えないが、敬老の日にスーパーにうじゃうじゃいたような年寄りにはならないと心に決めている。
オレが目指しているのは、これも上手くは言えないが、不穏な年寄りだ。
上手く言えない理由ははっきりしている。年寄りのロールモデルがないからだ。
長寿社会、結構なことだ。でも、みんな、年寄りになっちゃったあとの長い(かもしれない)時間をどう生きていいかわからないのではないか。何がかっこよくて、何が無残かわからないのではないか。
文学の、芸術の役割が、モデルの創出であった時代があった。〝青年〟のモデルを創出したのは、夏目漱石の「三四郎」、森鴎外の「青年」だった。明治から大正はじめにかけて〝青年〟というもののロールモデルが小説によって提示され、作られたのだ。
これからの文学の、芸術の役割は、〝年寄り〟のモデルを創出することかもしれない。
敬老の日のスーパーにいた年寄りをつらつら眺めながら、そんなことをオレは思った。
〝年寄り〟のロールモデルの創出ね。それなら、オレでもできそうな仕事だ。