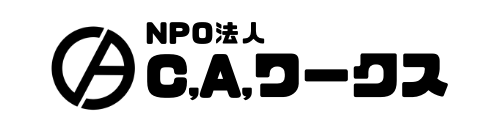『猫を捨てる』
オレはずっと、中根さん(76才)に聞こうと思ってたんだ。
「これからどうやって生きていくんですか」と。
一宮で知り合いになったばあさんたちは、そんなこと聞いたら絶対ダメだとオレを止めた。
「そのひと幾つ?76?そんなもん認知にならんこと以外、なんもないわ」ばあさんたちは豪快に笑い飛ばした。
76才の中根さん。
会社を60で定年して15年の中根さん。
かつての同僚との付き合いも絶え、家に籠もり、奥さんしか周囲に人はいない中根さん。
「趣味がない」と何度も繰り返し言う中根さん。
ばあさんたちが言うとおり、ホントに認知にならんこと以外、関心はないのだろうか。
珍しく定刻に着くと、中根さんはすでに会場にいた。
「遅くなりました」癖でオレはそう言ってしまう。自分の声が2重に聞こえた。今日の会場は声が響きすぎる。
「中根さん、お母さん、好きですか?」
「好きでも嫌いでもない」
「ご存命ですか?」
「えっ?」中根さんは左耳の補聴器を入れ直す。
「お母さん、生きてますか?」オレはつい大声になる。
中根さんは、少し笑いながら手を横に振る。
「お幾つでお亡くなりになりましたか」
「69」
「早かったんですね。中根さんはおいくつでしたか?」
「42、3」
「へえ」間抜けな返事をしてオレは口をつぐんだ。
お母さんは違う。ここに鉱脈はない。
毎回そうだ。どこをつつけば、中根さんがしゃべりだすのか。さっぱりわかならい。カチンと鉱脈に当たるまで、目くら滅法、つるはしを振り下ろし続けるしかない。
「お父さんは、生きてる?」
中根さんは、首を横に振った。今度は笑っていない。マスク越し(中根さんはいつもマスクだ)でも、真顔なのがわかった。
「お幾つで・・・」
「47」
「中根さんはそのとき・・・」
「19」
ここかもしれん。お母さんの話のときより、明らかに返事が早い。
「中根さん、ご兄弟は?」
「ひとり」
「一人っ子なんですか」
「そう」
「・・・どんなお父さんでした?」
「あんまりしゃべったことがない。家にいなかった。麻雀やりにいって。死んだ後、借金がたくさんあった」
「借金・・・。中根さんが返したんですか?」
「そう」
中根さん(76才)という人の人生が、突然オレの中で像を結んだ。それは実物の中根さんとは違うかもしれないし、3回会ったくらいで一人の人間を十全に理解できるなんて傲慢なことは考えちゃいないが。
19才で父親が他界した中根さん。
母親は内職をして家計を支えたが、自身も二十歳前から働きに出て、父親の借金まで返済した中根さん。
会社を2度変わったが、休みなく60まで働き続けた中根さん。
奥さんもらって、こどもを2人作り、その子どももちゃんと成人させた中根さん。
ギャンブルもやらず(「何やっても弱いんだ」と仰有った)、酒は好きだが溺れることもなく、76まで生きてきた中根さん。
「誰恥じることのない、立派な人生じゃないですか」何の企みもなく、言葉が口を衝いて出た。
誰も不幸にしていない。やるべきことをすべて全うした。なかなかできることじゃない。趣味がないとか友だちがいないって、すぐ言うけど、そんなこたあどうだっていいよ。あんたはよくやったよ。
「面白みのない人生だった」中根さんはオレの言葉に応じてそう言った。
自分の思いに入り込んで、危うく聞き逃すところだった。たまにかっこいいこと言うんだよ、あんたは。
オレはガマンできなくなった。一気呵成にまくし立てた。
「あのね、これ聞いちゃだめだって、一宮のおばあさんたちに釘さされてるけど、聞くよ。聞きたくなったから。中根さんさ、これからどうやって生きていくの?これは、どうしても聞きたかったんだ。中根さんのためじゃないよ、オレ自身のために聞きたいのよ。どう?これから、どうやって生きてくの?」
沈黙。でも、気まずくない。中根さんが考えているのがわかる。オレは、中根さんに思わずにじり寄る。ここ、ここだよ中根さん。
やっとここまでたどり着いた。オレは心底訊きたいことを訊いた。中根さんは何の義理もないのに、そんなことしたって一銭の得にもならないのに、苦手なこと(自分の思いを口にすること)に真正直に立ち向かってくれている。中根さんさ、おれは初めてあんたと対等に話している気がしてるよ、今。
「やりたいことを見つける」中根さんは言った。
一宮のばあさんたち、聞いたか。認知にならんようにするなんて、中根さんは言わんかったぞ。
オレは、なんでかわからないが、ざまあみろ、と思った。誰に対して?一宮のばあさんたちにじゃない。なら、誰に?わからない。強いて言えば、人生に対して、だと思う。
オレたちは、公民館の小さな読書コーナーに移動した。中根さんは本を読むのが好きだと言った。
なら、とオレは提案したんだ。いままであんまり読んだことのない本を読んでみませんか、と。オレもおんなじ本読むから、1ヶ月後、読んでどう思ったか、おしゃべりしませんか、と。中根さんはこくりと頷いた。
村上春樹の『猫を捨てる』をオレたちは選んだ。
カチリ。鉱脈につるはしの当たった音が聞こえた。
。