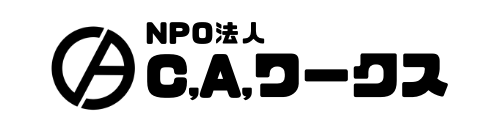『帰郷』バックストーリー②
夢見る人
時次郎は夢見る人であった。余人の思いつかないことをひらめき、それを粘り強く実現していった。時次郎が贖った自社ビルは地下1階地上5階で、6軒の同じつくりのビルが壁一枚隔てて横につながっていた。時次郎は中2階に目を付けた。どうせつながっているなら中2階だけ通り抜けられるようにして、6軒のビルを繋げてしまったらどうだろう。6軒が一つの大きなビルのようになったら、お客は面白がるんじゃないか・・・。今でいう大規模ショッピングモールの発想である。商店街は元来、個人商店の集合体である。時次郎の発想は画期的なものであった。6軒のビルの中2階の部分に穴を開け、繋げる工事が始まった。資金繰りも工事の手筈もすべて時次郎が担った。商店街からは思っていた以上の反発を受けた。「常時繋げていなくてもいい、何かの時には、それぞれのビルが独立して商売できるよう、開閉自在の大きなシャッターを中2階の通路に取り付けたらどうか」反対派を黙らせるために時次郎はまた新たなアイデアを捻り出した。このアイデアを実現するために更に多くの時間と金が必要となった。時次郎は市内の銀行に日参し、自分のビルを抵当に入れて、シャッターを取り付けるための工事費用を捻出した。
時次郎の目論見は当たった。1年後、1つのショッピングモールのようにつながった6軒のビルには人が溢れた。中2階の通路は、訪れる買い物客が多すぎて大渋滞を引き起こした。「こんなことなら」工事に猛反対していた商店街の主人が時次郎に言った。「いっそ全部の階の壁を、ぶち抜いてしまえば良かったのに」
儲かること。そのためには客を呼び込むこと。これができることが、商売人の正義であった。26歳の時次郎は、ほんまち通り商店街で知らぬ者のない存在になっていった。
瓦解
平成12年(2000年)、時次郎27歳。名鉄東一宮駅が突然移設した。駅は廃止され、現在の一宮駅南口に名鉄百貨店も移った。それまでは東一宮駅が一宮の中心であった。そして駅と真清田神社を一直線につなぐ本町商店街が一宮の中心であった。一夜にして人の流れが変わった。本町通商店街から、人の流れが消えた。あっという間だった。
平成13年(2001年)、時次郎28歳。商店街のアーケードの大改修が完成する。市長を呼んで盛大に式典も取り行なった。「これでもう一度、勝負ができる」時次郎たち商工会青年部は意気込んだ。
しかし、一旦変わった人の流れはそう易々とは戻ってこない。フロア貸しをしていたテナントも賃料が払えず撤退し、代わりが入っても定着せずにまた撤退する、ということが繰り返されるようになった。地下1階地上3階の店舗フロアに、母の洋品店と時次郎の喫茶「まちぶせ」しか店がない状態が出来したのは、時次郎が32歳の時、平成17年(2005年)であった。6軒のビルをつないでいた夢の通路にもシャッターが下ろされた。隣のビルの主人が、もう商売はやらないと言い出したからである。
商店街にはシャッターを下ろしっぱなしにする店が目立ち始めた。「アーケードはシャッター街になった」一宮市民は平気で口にした。「普段の買い物は仕事帰りに駅構内のスーパーで済ませるし、ちょっといいものは駅の隣の名鉄百貨店に行くかな。遊びに行くのは名古屋ね。だって急行に乗れば、ひと駅10分で名古屋駅だもん。名鉄が移転してくれてホントに便利になった。商店街?あのアーケードがある?七夕まつりのときに行くくらいかなあ。だって、あそこさ、普段はシャッター街なんだもん」
名鉄移設からわずか5年。街の中心は完全に駅ビルに移ってしまった。
それでも時次郎は諦めなかった。「店は商品を売るんじゃない。夢を売るんだ」時次郎は常々言っていた。彼は喫茶「まちぶせ」を決して閉めようとはしなかった。一人もお客が来ない日が続いても閉めようとはしなかった。蝶ネクタイに、大きなタータンチェック柄の派手なベストを着て、ベレー帽をあみだに被った時次郎がぽつねんとカウンターの中で本を読んでいる姿が、人通りの絶えた通りからよく見えた。母の洋品店はすでに時代遅れとなり、安価で大量生産の大型衣料品店に客足は流れた。母は店を維持したまま、奥でミシンを踏むアルバイトを始めた。ペット用品を作る下請けの仕事であった。自社ビルを建てた時の借金はまだ残っていた。妻は採用試験を受け、一宮市の職員となった。一家が暮らしていきながら、借金を毎月返済していくためには、現金収入がどうしても必要であった。
客足が遠のき、老齢化と後継者不足も目に見えて深刻になった商店街にあって、若い時次郎は希望の星と目されていた。推されて商工会の役員の仕事をするようになった。推されると時次郎は断れない。心ならずも「まちぶせ」を休業する日が次第に多くなっていった。
(『帰郷』バックストーリー③へ続く)