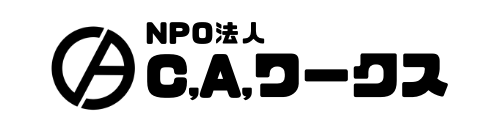老い
おれの母親は見栄っ張りで、自由に歩けるうちはかつらを被っていた。それはそれはうまくできたかつらで、80過ぎのおしゃれに気を遣っている女性はかくやと思わせるような出来のかつらだった。ちょっと白髪になっていて、ほんの少しだけ髪のボリュームも落ちていて。元気に動き回っていた頃の母親と、おれはほとんど没交渉だったが、母親がかつらをかぶっているなどとつゆ思わなかった。だから驚いたのだ。歩けなくなって、介護ベットに寝かされた母親を初めて見た時に。真っ白な髪。皺しわな口の辺り。ピンク色がグラデーションでほんのり入ったディオールの眼鏡をはずした母は、おれの知っている母親とまるで違っていた。これ、誰?誇張ではなくおれは本当にそう思った。枕元に、人形のアタマに被せて、かつらが置かれていた。母親のいつものヘアスタイルだった。かつらを見て、やっと目の前の老婆が母親であると腑に落ちた。そんな姿をおれに見られて母はどんな気分だったろう。歩けなくなり介護ベットでずっと寝てる生活になったのだから、もう気分も、見栄も何もありゃしなかったのかもしれないが、それでもおれはあのかつらを外した姿をおれに晒した日から、母の中で何かが終わったような気がする。老いが母親を真にとらえたのはあの日からだった気がしている。