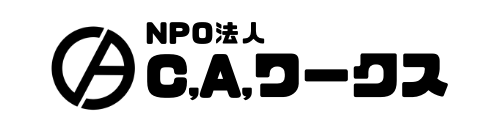学校
定時制高校には感謝している。こんなオレを20年も置いてくれている。
20年前も今も、定時制高校は社会の縮図だ。
20年前、オレが赴任したころは、ずいぶんと荒れていた。それが、ぐんぐん不登校の生徒が増えて、在校生の6割を占めるようになった。そして今は、多様な、本当に多様な生徒が通う学校に変った。
不登校の生徒が多数を占めるころ、オレは「演劇表現」という授業を始めた。演劇部の活動に気が狂ったようにのめりこんだ。
生徒の層が変わり始めたのが顕著に感じられ始めたころから、オレは「リベラルアーツ国語」という授業を準備し始めた。そして今年度1年間、実際に授業を実践した。
オレね、定時制高校に恩返しがしたいんだ。長く置いといてくれたことへの恩返し。そんな気持ちで「演劇表現」も「リベ国」も作った。
生徒が、変わるといいね。どう変わっても、何ができるようになってもいいんだよ。授業を通して、クラス活動を通して、部活動を通して、先生と生徒、生徒と生徒がやり取りする中で、変わって行ける場。それが学校だと思う。定時制高校って、生徒がこの世に取り付いてゆくために、変わってゆくことを目指す場所だと、オレは思う。
一つ文章を引用する。ウチの学校の生徒が、定時制通信制の生活体験発表大会というのに出場した時に読んだ原稿だ。オレが添削指導した。
オレの学年の生徒で、なおかつ演劇部員だった。ずいぶん長い時間を、この生徒とはいっしょにすごした。卒業した今でも付き合いがある。
なぜ引用するか。変わるってどういうこと、学校の役割ってどういうこと、っていうのが、一人の生徒のナマの言葉によく結実されているからだ。この生徒は、ウチの学校に来て、演劇部に入って、本当に良かったんじゃないか。この生徒には、学校らしいこと、教員らしいことをしてやれたとオレは思っている。
『僕は靴紐が結べなかった。高校の入学式は、紐を床に垂らしたまま出た。そんな新入生は僕一人だった。
中学の間、僕は引きこもりだった。パソコンをいじって過ごした。コンピューターが特に好きだったわけではない。時間つぶしだ。
誰にも会わない暮らしは気楽だった。でも、その間にすごく差がついた。普通のことが普通にできなくなってしまった。鉛筆で字を書く。漢字どころが、引きこもっているうちに、ひらがなを書くのさえ、僕は苦労するようになっていた。
高校の入学式で校長先生が言った。
「学校はできないことをできるようにする場所です」
僕は、この言葉を信じてみようと思った。
「学校は、できないことを、できるようにする、場所です」
入学式が終わった日の夜、家のベットの中で決心したのを今でもはっきり覚えている。
「学校はできないことをできるようにする場所です」
そうか。できないことをできるようにする場所なのか。なら、学校という場所は、僕のような、何もできない人間のためにあるんだなと。できないことをできるようにする努力を続ける限り、靴紐すら結べない、ひらがなすらロクに書けない、こんな僕でも、高校生をやってていいんだなと。
僕がまずトライしたこと、それは靴紐を自分で結ぶことだった。十五年間できなかったことが、やってみるとわずか十五分でできるようになった。
次にバスと電車の乗り方を覚えた。切符の買い方を駅員さんに教えてもらうのは少し気が引けたけど、とても親切に教えてくれた。
人と話すこともできなかった僕は、会話術の本を読み漁り、活舌をよくするために、文章を声に出して読んで練習した。
生まれて初めて部活動にも入った。演劇部だ。一つの芝居をいっしょに創ることを通して、先輩や顧問の先生にいろいろ教わった。大事だと思うことは必ずメモをした。メモは今でもすべて取ってある。最初の頃はひらがなばかりの下手くそな字だけど、それでも僕の宝物だ。
一年の冬には中部大会に役者として出た。全日制の大会で、中部ブロック300校の演劇部のうち、上位17校しか出られない大会だ。「引きこもってしまった人間が、もう一度顔を上げ、外の世界に出てゆくにはどうしたらいいか」というテーマの芝居だった。これ、自分のことだ。そう思って、一生懸命頑張った。緊張しすぎて、芝居の最中に鼻血を出したこともある。でも、最後までリタイアすることなくやりきった。人前に立つことがとても怖かった自分にとって、舞台はその怖さを克服する得難い場所になった。
大会が終わった後、顧問の先生が言ってくれた。「何もできなかった昔のお前を、今のお前が見たら、笑ってしまうだろうな」
顧問の先生の言葉を聞いて、遠くまであるいてきた自分を初めて実感した。季節はいつの間にか冬になっていた。靴紐すら結べなかったあの入学式の日から、一年が経とうとしていた。
二年生になると、ともだちができた。ともだちができたのも僕にははじめてだった。今ならわかる。ともだちというのは、意を決して頑張って作るものではなくて、同じ場所にいて、同じことをする間にいつの間にか、ともだちになっているものなんだと。ともだちはつくるものではなく、なるものなんだと。もちろんたくさんいるわけじゃない。他愛のない話をしながら刈谷駅まで帰るだけだ。でも一緒にいて楽しい。時に自分の思うように反応してくれなくて、もどかしかったりするけど、それでも楽しい。パソコンは一緒にいてもこんなふうには楽しくはなかった。もどかしくはないけど、ともだちのようには楽しくない。
ともだちと話していると、刈谷東高校にはいろんな境遇の人が通ってきていることがわかる。親とうまくいかなかったり、アルバイトをして、そのお金で学校に通って来ていたり。外国籍で日本語に苦労している子もいる。僕と同じように人が苦手で苦しんでいる生徒もたくさんいる。
自分以外のひとのことを想う、これも僕には初めての経験だった。これまでしたことのないことだった。そうして気づいた。できないことをできるようにしようと頑張っているのは、僕だけじゃないんだと。刈谷東高校に通っている生徒は、みんなが自覚しているわけではないかもしれないけれども、今の自分じゃない自分になろうとして、学校に通ってきているんだなと。そう考えると嬉しい。ここが、この学校が自分のいていい場所に思える。同級生のみんなを仲間だと思える。こんな思いも中学までは持ったことがなかった。初めての思い、初めての、経験だ。
僕はまだまだダメダメで、できないこともたくさんある。時に疲れ果て動けなくなってしまうこともある。そんなときは、家のベッドの中であの言葉を思い出してみる。入学式のあの日と同じように。そうすると、またゆっくりと立ち上がれる。きっと立ち上がれる。何度でも何度でも。この言葉は、僕の人生の杖になった。
「学校はできないことをできるようにする場所です」
ご静聴ありがとうございました。』
こういう経験をする生徒をひとりでも多く育てる。変わる機会を授業という形で提供する。「リベラルアーツ国語」とはそういう授業だ。