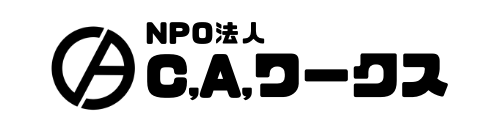モノには記憶が宿るのかも(2)
『便所くん』はオレにとって大事な芝居だ。
2004年12月、オレは「Making of『赤い日々の記憶』という芝居で文部科学大臣賞を取った。昼間定時制高校の演劇部が60年ぶりに全国大会への出場を決めた瞬間だった。不登校経験者ばかりの演劇部員に、不登校を演じさせる。朗読劇のような体裁の芝居の作りになっている。セットは一つもない、照明もベタとSSのみという徹底した簡素な舞台つくり・・・。あの時の審査員は、こんな変わった芝居をよくぞ最優秀賞に選んだものだ。心底有難いと思っている。
全国大会に行ったことで、オレは悪口を言われるようになった。曰く『不登校を売り物にしている』、曰く『台本読んでるだけじゃん、あんなの』、曰く『あれは芝居ではない』・・・。悪口を言われることが、言われた側の性格にどれだけ暗い影を落とすか、生きる意欲を削いでゆくか、オレは初めて実感した。怖くて外も歩けない。見ちゃダメだとわかっているのに、不安で不安で仕方なくて、つい掲示板を見てしまう。で、また悪口を見つけて怖くなる。ズドーンと落ち込む。夜も眠れなくなる。浅い眠りについても悪夢にうなされ飛び起きる。寝汗をびっしょりかいている・・・。オレがこんな性悪になったのも、オレの知らんところで悪口の限りを言われ続けたせいだ。オレがオマエらになんの悪いことをした?オレだって人間だからね、匿名でネットで好き放題言いやがって!
そんな悪口の洪水の中で、オレが一番カチンときたのは、『兵藤は、ちゃんとしたストーリーが書けないから、あんなノンフィクションみたいな芝居を作ったんだ。まぐれ当たりだ』という言葉だった。
オレも40前の、まだまだ血の気が多い時期だったから、「ストーリーラインのはっきりした芝居なんてちょろいもんだ、そんなもんすぐに書けらあ」と息巻いて、オレを悪く言う高校演劇関係者を呪う気持ちをエネルギーに変えて書き上げたのが、『便所くん~男だけの世界~』という芝居だった。
2007年冬、地区合同発表会で初の上演。翌2008年冬、中部大会で勝ち残って全国大会出場決定。翌2009年、全国大会出場。オレは物語も書けるんだと満天下に見せつけてやったわけだ。ざまあ見やがれ。
前置きが長くなった。とまあ、こんな経緯で、便所くんという人格はこの世に誕生したのだ。
以来、2009年『便所くん2~ボクの友だち~』、2010年『断絶~便所くん最期の日~』と便所くんシリーズは続いた。
『便所くん2』では、便所くんは3メートルの巨大男性便器に姿を変えていた。人が怖くて外に出られない自分が恥ずかしい。でもやっぱり人目は怖い。葛藤と自己嫌悪。便所くんの自我は肥大を続け、果てはその姿を内心にふさわしいものに変えてしまった。ちょうど『山月記』の李徴が、臆病な自尊心と尊大な羞恥心を肥大させて、虎に姿を変えたように。
『便所くん最期の日』では、3メートルの便所くんは世界征服をたくらんだ。世界中がみんな引きこもりになってしまえば、引きこもりの自分を恥じることもなくなると、発想を転換させたわけだ。だが、一人の少女との戦いに敗れ、便所くんは、表舞台から姿を消した。
便所くんの生みの親であるオレが、便所くんの雄姿を最後に目にしたのは、2010年冬、富山県で開催された中部大会の舞台だった。
あの日から14年の歳月が流れた。
3メートルの巨大男性便器である便所くんは、あの日からずっと、刈谷東高校の工業棟の倉庫の片隅で横たわっている。人目に付かぬよう四方をロッカーに囲まれて。
この長い長い年月、誰も便所くんを気に掛ける人はいなかった。いや、オレはずっと知っていた。便所くんはあそこにいると。まるで忌むべきもののように、掃除道具入れのスチールのロッカーで結界を張られて、それでも確かに便所くんはそこで生きているのだと、オレは知っていた。知っていて、オレは会いに行こうともしなかった。日々の仕事に追われて?そうかもしれない。会いに行くのが怖かった?そうかもしれない。うん、きっとそうだな。オレは怖かったのだ。理由ははっきりとはわからないが。でも、これだけは間違いない。生みの親であるオレにすら、便所くんは見捨てられたのだ。オレは、自分のプライドを満たすために便所くんを生み出し、さんざん使い倒したあげく、見捨てたのだ。
便所くんは、この14年の間にこの世界に起こったことを何も知らないのだ。2011年から急速に普及したスマートフォンのことも、2020年から2023年まで世界的に大流行したコロナのことも、コロナがきっかけとなって、人と人との付き合い方が劇的に変化したことも、便所くんは何も知らないのだ。
2024年春、一人の少女がふらりと工業棟にやってきた。
外は五月晴れ、抜けるような青空だ。その青さが少女には疎ましく感じられる。ここはいい。落ち着く。少女は思う。ひんやりして、薄暗くて、誰もやってこない。人間は、疎ましい。
少女はロッカーにもたれて、アイフォンから音楽を小さく流した。RCサクセションの『スローバラード』。むき出しのコンクリートの壁に反響して、空間全体から音楽が降ってくるように感じられる。いいとこを見つけた。少女は目を閉じて、音楽に身を浸らせる。
と、忌野清志郎のボーカルの合間に、泣き声が、男の子の泣き声がどこからか聞こえてきた。泣き声は次第に大きくなって・・・
こうして少女と便所くんは出会った。便所くんは14年ぶりに、生きた人間に出会ったのだ。(つづく)