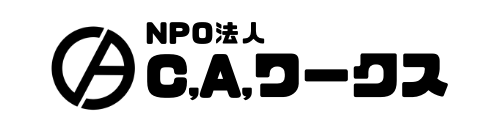「性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く」
「隴西の李徴は博学才頴、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった。」
かつての国語の教科書の定番作品『山月記』の冒頭部分だ。
どんだけこの小説の授業やったことか。『羅生門』、『山月記』、『こころ』、『舞姫』なんてのは、国語教科書の定番で、かつては、いったん教材を作っちゃえば、、古ぼけて、よれよれになっちまったプリントを使いまわしさえすりゃあ、定年するトシまで授業やっていられたんだ。なんちゅうラクな商売だろうね、国語の教員ってのは。
だから猛反発したんじゃないのかね、新学習指導要領になった時に。やべえ、古ぼけたプリント、もう使えないじゃん!ってさ。新学習指導要領で必修科目になった「現代の国語」には、定番の小説教材がまったく載ってないからね。
いるんだよ、実際。『羅生門』は暗唱するくらい詳しいけど、『鼻』は読んだことすらないとか。『舞姫』の話は口角泡を飛ばして、あるいは優雅に紅茶でもすすりながら延々と御託を並べるくせに、『うたかたの記』は存在すらも知らないとか。そういう、年取った国語の教員が。扱っている教材のことしか知らない、おんなじプリントをずっと使いまわすって、インチキ野郎だとオレは思う。あのさ、肉屋は肉一般について詳しいんじゃないの?魚屋は自分の店に置いてない魚のことだって知識あるんじゃないの?扱っている教材以外は読んだこともないって、やっぱりインチキ野郎だよ。職業倫理に悖るよ。
話を「山月記」に戻す。
「性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く」。簡単に言い換えると「性格は頑固で、自分の信じるところを固く守って他人に心を開こうとせず、自分の能力に絶対的な自信を持っている」くらいの意味かな。主人公の李徴の性格を定義した箇所なんだけど、この一節をね、授業で扱うたびにオレは思ってたんだ。「これ、オレのことだ」って。「(主人公の)李徴は、オレだ」って。
いつからそんなになったんだろうって思うね。オレは元々、うすぼんやり子供だったんだよ。人にすべてを任せきっててさ、自分の考えってもんを全く持ってないような子供だった。多少の感情の波立ちはもちろんあったよ。でも、それほど大きな不満も怒りも、感じたことなかったんじゃないか。少なくとも小学校、いや、中学2年まではそんな子供だった。
とまれ、今は、いや、大人になってからずっとだな、オレは「性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く」で通して来た自覚があるよ。
こんな固い姿勢をとってきたおかげで、手に入れたものもたくさんあった。その一方で、手に入れ損ねたもの、失ってしまったものもたくさんあった。
馴染んだ姿勢を変えるのは難しい。それでも、オレは今、このトシになって「性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く」のままじゃあ、太刀打ちできない事業を始めようとしてるところだ。古いプリントを平然と使い続ける、年寄りの国語の教員を口を極めて罵った限りは、オレはおなじ轍は踏まない。オレは、「性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く」ではない自分に変わろうとしている最中だ。変な言い方かもしれないけど、気分は、さあ勝負だって感じなんだよ。
人は未来に向かって開けているほうがいい。いくつになっても自己否定の衝動を身の内に抱えていたほうがクールだ。このトシになって、そんな勝負ができることは幸せなことだし、ワクワクしているよ。